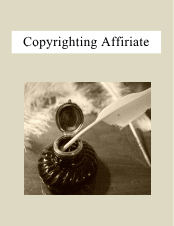小説の出だし、冒頭文の書き方に学ぶ文章を読ませるテクニック。
宇崎です。
今回は小説や文学作品の「出だし(冒頭文)」から、
「文章を読ませるテクニック」
にあたるものを言及してみたいと思います。
有名な小説や「名作」と言われる文学作品は、
やはりその出だしとなる冒頭文から光るものがあり、
「読者を即座に引き込むテクニック」
がさりげなく用いられている傾向にあるんです。
ただ、それは作者が「意図的」にそうしたのか、
意図しない文章が結果的にそういう文章になったのか、
それは作者以外、知る由もないところかと思います。
何せ、そういう小説や文学作品を世に残した人は、
いわゆる「天才」と言われる文豪達がほとんどですからね。
ですが、これから挙げていく有名な小説や文学作品などには、
その出だし(冒頭文)に共通するものがありますので、
今回の講義では、そのような天才達が手掛けた文章から、
「読者を引き込む文章のテクニック」
にあたるものを紐解いてみようと思います。
|
このブログで扱っているテーマはあくまでも、 「コピーライティング」 であり、文章によって読み手を反応させるスキルや、 それに準じたテクニックにあたるものです。 ただ、そのコピー(文章)で実際に反応を得るには、 大前提として、それをまず読んでもらう必要があります。 商品の広告(販売)などを担うコピー(文章)は、 読んでもらえる事が前提になるわけではないからです。 故にコピー(文章)は「読まれない事」を前提とした上で、 「読ませる事(興味を引く事)」 を意識して見出しや冒頭文を構成する必要があり、 これが最初に超えるべき「消費者心理の壁」にあたります。 コピーライティング界隈では、 ・興味の壁(Not Read):読まない ・信用の壁(Not Believe):信じない ・行動の壁(Not Act)・行動しない これが消費者心理における3つの壁と言われていますが、 今回の講義はこの3つの壁の中の「最初の壁」である、 興味の壁を超えるテクニックを言及するものだという事です。 |
それでは、早速、いってみましょう。
小説の出だし、冒頭文の書き方に学ぶ文章を読ませるテクニック
まず、結論的なところから言ってしまうと、
多くの有名な小説や名作と言われる文学作品の多くには、
その出だしの冒頭文に以下のような共通点があります。
・感覚(五感)に訴えている
・普遍的なテーマを意識させている
基本的には、この「どちらか」に当てはまる出だしから始まり、
読者を物語へと一気に引き込むような構成になっているわけです。
もちろん、全てがこのどちらに当てはまるわけではありませんが、
わりと、このどちらかのテクニックを使っているものが多く、
前者の「感覚(五感)に訴える構成」は以下のようなものです。
|
道がつづら折りになって、いよいよ天城峠に近づいたと思う頃、雨足が杉の密林を白く染めながら、すさまじい早さで麓から私を追ってきた。 ―『伊豆の踊子』川端康成 |
|
国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。 夜の底が白くなった。信号所に汽車が止まった。 ―『雪国』川端康成 |
|
「おい地獄さ行ぐんだで!」 二人はデッキの手すりに寄りかかって、蝸牛が背のびをしたように延びて、海を抱え込んでいる函館の街を見ていた。 ―『蟹工船』小林多喜二 |
|
朝、食堂でスウプを一さじ、すっと吸ってお母さまが、 「あ」 と幽かな叫び声をおあげになった。 ―『斜陽』太宰治 |
|
飛行機の音ではなかった。耳の後ろ側を飛んでいた虫の羽音だった。 ―『限りなく透明に近いブルー』村上龍 |
いずれも有名小説や名作と呼ばれる文学作品の出だしの一文ですが、
これらは主に「視覚」か「聴覚」または、その「両方」の感覚に訴え、
そのイメージを頭の中で描けるような冒頭文になっている事が分かります。
川端康成などは、上記以外も「描写形」の冒頭文が多い作家なので、
もしかすると、意図的にこの手法を使っていたのかもしれません。
また、上記で挙げた『蟹工船』などに見られる、
「台詞」
から始まる冒頭文もわりと王道的なもので、
それ自体が、その台詞が耳に入るような感覚や、
その「会話」のイメージを広げ易い傾向にあるため、
台詞が出だしとなっている小説はわりと多い傾向にあります。
このような視覚、聴覚など感覚に繋がる文章は、
それらによって頭の中に「イメージ」が広がる事となり、
そのイメージによって読者は物語に引き込まれる事になるのです。
感覚(五感)に繋がる文章で読み手を引き込む。
対して、出だしの冒頭文で
「普遍的なテーマを意識させているもの」
としては、以下が該当すると思います。
|
永いあいだ、私は自分が生まれたときの光景を見たことがあると言い張っていた。 ―『仮面の告白』三島由紀夫 |
|
死のうと思っていた。 ―『葉』太宰治 |
|
山椒魚は悲しんだ。 ―『山椒魚』井伏鱒二 |
三島由紀夫の『仮面の告白』は「生(誕生)」というテーマ、
太宰治の『葉』は「死」という普遍的なテーマを意識させています。
井伏鱒二の『山椒魚』は「悲しみ」という普遍的なテーマに、
山椒魚という本来は感情を持たない生き物を絡ませて、
ある種の「意外性」を持たせていますね。
ただ、いずれも「続き」が気になってしまう冒頭文ではないでしょうか。
やはり、このような普遍的なテーマにあたるものには、
誰もが少なからず「興味」や「関心」があるため、
それを意識させる冒頭文には引き込まれてしまうのだと思います。
ちなみに私は最初に例を示した感覚(イメージ)に繋がるものよりも、
後者の「普遍的テーマ」に繋がるものの方が引き込まれるのですが、
この「両方」を押さえている冒頭文が以下などです。
|
死者たちは、濃褐色の液に浸って、腕を絡みあい、頭を押しつけあって、ぎっしり浮かび、また半ば沈みかかっている。 ―『死者の奢り』大江健三郎 |
|
「完璧な文章などといったものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね。」 ―『風の歌を聴け』村上春樹 |
|
さびしさは鳴る。耳が痛くなるほど高く澄んだ鈴の音で鳴り響いて、胸を締めつけるから、せめて周りには聞こえないように、私はプリントを指で千切る。 ―『蹴りたい背中』綿矢りさ |
大江健三郎の『死者の奢り』は「死後の世界」というテーマに、
視覚的なイメージが広がる描写を文章にしたもの。
村上春樹の『風の歌を聴け』は「絶望」というテーマに、
台詞を出だしの冒頭文に使うテクニックを重ねているもので、
綿矢りさの『蹴りたい背中』は「さびしさ」をテーマに、
聴覚と視覚のイメージに繋がる文章が構成されていると思います。
もちろん、ここで挙げたものは、ごく一部でしかありませんので、
・感覚(五感)に訴えてイメージを引き出す
・普遍的なテーマを意識させる
このいずれか、もしくは両方を押さえて、
その出だしの冒頭文を構成している小説や文学作品は、
本当に数えきれないほど、多くあるわけです。
そして、これらの要素を押さえた文章の有効性は、
コピーライティングの観点でも全く同じ事が言えます。
・鮮明なイメージが膨らむ文章
・普遍的なテーマを意識させる文章
これらに相当するコピーは読み手を一気に引き込み、
その続きを読ませる上でも極めて有効であるという事です。
少なくとも、これらのテクニックを用いた「事例」にあたるものは、
多くの有名な小説や名作と呼ばれる文学作品で確認できるはずですので、
今後は、そのような視点でそれらに目を通してみてください。
また、違った気付き、学びを得られるはずです。
K.Uzaki
>コンテンツ一覧へ
タグ
カテゴリー:文学に学ぶコピーライティング