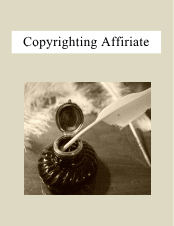行動心理学「アンカリング効果」とは、その事例。
アンカリング効果は行動心理学原理の1つで、
物事の意思決定において最初に提示された条件や数字によって
その条件が基準となる事でそれ以降の意思決定を
先立って刷り込まれた基準に合わせて行ってしまうというものです。
要するに人は最初に提示されたの数字や条件を
次以降の物事の判断における基準にしてしまうという事。
このアンカリグ効果を狙ったマーケティング手法は
情報商材のセールスレターなどによく使われていますね。
アンカリング効果のマーケティング活用事例
最初に高額な価格設定をふっかけておいて、
何やかんや理由をつけて安い値段を提示する、とかです。

高い金額を最初に提示されると、
読み手はそれを基準に意思決定をするようになるので、
その後に安い金額を提示すれば、
最初から安い金額を提示するより遥かに
その金額に対する印象を「安い」と思わせられます。
アンカリング効果の行動心理学事例
日常的な使い道として人に何かお願いをする際などは
このアンカリング効果を利用していくことが出来ます。
最初の段階で到底受け入れてもらえいないようなお願いをして、
その後で本来頼みたかった頼みごとをするわけです。
すると物事の判断基準が高いところから低いところに下げられ、
普通にその物事をお願いするよりも、
相手に受け入れてもらえる可能性が高まるというわけです。
これもまた同じような原理をセールストークでも使えますね。
まあ、アンカリング効果という名称はともかく
この行動心理学の原理は既にある程度は知られていますので
見え見えの誘導は関しては逆効果になる可能性も否めません。
それをいかに自然に行うかが重要になるという事です。
それもまたライティングテクニック次第という事ですね。
認知度はそれなりに高いものの
やはり効果的なテクニックである事は間違いありませんので、
セールスを行っていく際はネット、リアル共に使えるテクニックです。
是非活用してみてください。
K.Uzaki
>コンテンツ一覧へ
タグ
2014年1月1日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:行動心理学
行動心理学フレーミング効果(フレーミング理論)マーケティング活用。
人は実質的には全く同じ内容の選択肢を迫られても
その表現方法などの違いによって、
統計的にかなり偏った判断を行っていくという事が
多くの心理学実験などでも立証されています。
下記がその選択肢の事例です。
フレーミング効果(フレーミング理論)の事例
ある伝染病に1万人の人が感染してしまい、
そのまま放置してしまうと全員が死んでしまう。
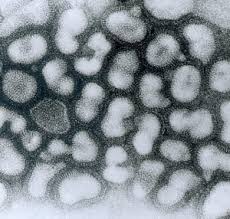
その対策案としてA案とB案が提示された
下記2つのような内容でそれぞれの案が提案された。
(提案方法1)
・A案:300人が助かる。
・B案:70%の確率で全員が死亡する。
(提案方法2)
・A案:700人が死亡する。
・B案:30%の確率で全員が助かる。
A、Bそれぞれの提案内容は全く同じものです。
ただそれぞれの言い方が異なるだけで、
提案方法1の場合、多くの人はA案を選択し、
提案方法2の場合、多くの人はB案を選択します。
おそれぞれの言い方の大きな違いは
「助かる」というポジティブな言葉の印象と、
「脂肪する」というネガティブな言葉の印象からくるもので、
2つの選択肢を迫られた場合など、
人はポジティブな表現の選択肢を選ぶ傾向にある事が分かります。
フレーミング効果(フレーミング理論)のマーケティング活用
人に何かを提案していく際、
その方向に向けて「YES」を受け取りたい場合は
同じ提案でもポジティブな表現を主に用いるべきであり、
逆にあえて遠ざけたい提案などがある場合は
ネガティブな表現を用いていく事が有効という事になります。
これはコピーを作成していく上でも
ちょっとした言い回しの違いで
その反応を大きく変えられるポイントでもありますので、
これらの心理効果を出来るだけプラス材料に使ってみてください。
このブログを読んでいる人の80%が、
新しい心理学の知識を有効に活用出来たと言っていますので(笑)
K.Uzaki
>コンテンツ一覧へ
タグ
2013年12月29日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:行動心理学