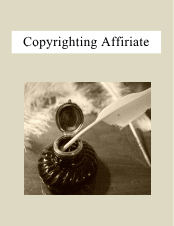川端康成の文学小説、文章に学ぶ美し過ぎる情景描写、比喩表現
言葉の使い方、文章が「美しい」と表現される作家と言うと、
やはりノーベル賞作家の川端康成の名前が挙がると思います。
とくに私が川端康成の小説、文章を読んでいて思うのは、
「情景描写が上手いとか、もはやそういうレベルを通り越している」
という事です。
作家が物語を書くときは様々なものを文章で描写しますが、
川端康成はとにかく「情景描写が神がかっている」と思います。
コピーライターがコピーを書くときも何かを描写する事はありますし、
当然、情景描写に近いものをコピーにするような事もあります。
ただ、文章における「描写の美しさ」のようなものに関しては、
最終的にはセンスやその人個人の美的感覚が大きいのかもしれません。
そういう意味では参考にして書けるものではないのかもしれませんが、
文章でこんなにも美しい情景描写ができるといった視点も含めて、
「川端康成の情景描写3選」
というテーマで、私が個人的に記憶に焼き付いた、
川端康成の情景描写を3つほどご紹介していきたいと思います。
川端康成の文章に学ぶ、美し過ぎる情景描写、比喩表現。
私が選んだ情景描写3選の前に、川端康成の文章を語る上では、
「まずはこれをご紹介しておかなければ始まらない」
という、有名なこちらの文章をひとまず紹介しておきます。
|
国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった。 -川端康成「雪国」より |
これはもはや、私があえて言及するまでもないくらい、
多くの人、作家などが、その「凄さ」を解説している有名な文章です。
小説そのものも有名な『雪国』の最初(書き出し)の一文ですが、
この有名な文章も、他でもない「情景描写」にあたります。
やはり卓越しているのは『夜の底が白くなった』の2つ目の文章で、
「夜」「底」「白」
といった、誰もが普段から日常的に使っているような言葉だけで、
誰も書いた事がないような表現を「自然な表現」のように文章にしている事。
「夜の底」「夜が白くなる」
このような表現はまずしないはずなのですが、いざ文章を読んだ際、
そんなありえない表現をごく自然に捉える事ができます。
使った事も聞いた事もない表現であるにもかかわらず、
その情景、状況が頭の中で普通にイメージできてしまうわけです。
「夜の底が白くなった」という、この短い一文だけで、
ここまで「凄さ」を言及できてしまうのですから、
さすがはノーベル賞作家ということですね。
一応、この一文に学ぶ事ができる「情景描写」のポイントとしては、
・誰もが日常的に使っている言葉だけを使う(耳慣れない言葉は使わない)
・日常的な言葉だけで全く新しい表現で文章を構成する
・その表現が自然と頭の中に入ると共にイメージできる文章にする
という感じになると思いますが、こんな文章はそうそう書けないと思います。
ただ、この『雪国』の書き出し文は、あまりにも有名ですから、
実際に『雪国』を読んだ事がない人でも目にした事があるような文章です。
当然、川端康成の文章には、これにも劣らないような凄い文章、
美しい情景描写がたくさんありますので、ここからは私が選んだ、
「川端康成の凄いと思う情景描写3選」
を紹介していきます。
川端康成の「凄い」と思う情景描写①
|
谷には池が二つあった。下の池は銀を溶かして称えたように光っているのに、上の池はひっそり山影を沈めて死のような緑が深い。 -川端康成「骨拾い」より |
これは少し不気味さを感じさせる情景描写ですが、
・誰もが日常的に使っている言葉だけを使っている
・日常的な言葉だけで全く新しい表現の文章を構成している
・その表現が自然と頭の中に入ると共にイメージできる
という点は、やはり共通している文章だと思います。
この文章は「2つの池」について描写しているわけですが、
・銀を溶かして称えたように光っている池
・ひっそり山影を沈めて死のような緑が深い池
池の描写で、手短に、ここまでの文章を書けるのは
やはり「凄い」としか言いようがありません。
それこそ長々と様々な比喩や表現を駆使して長い文章を作っていけば、
かなり具体的なイメージが広がる「池」を描写する事ができると思います。
ですが、川端康成の文章は、それを物凄い短い文章でやってしまうわけです。
とくに2つ目の池の描写は「死のような緑」という、
これまた誰も使わないような表現が「自然」に使われています。
「死」という概念と「緑」という色の組み合わせが、
ここまで「池」の情景描写にハマるなんて、
少なくとも、私はこんな描写表現は絶対に考え付かないです。
川端康成がこういう表現を頭を捻って考え出していたのか、
それとも、こういう表現が自然と出て来る人だったのかはわかりません。
どちらにしても「もの凄い表現力」だと思いますが、
日常的に「池」や「海」などの自然を目にした際、
「死のような緑だな」
という感覚が自然に出て来るような人だったのであれば、
もはや天性の感覚を持っていたとしか言いようがないですね。
川端康成の「凄い」と思う情景描写②
|
若葉の影が令嬢のうしろの障子にうつって、花やかな振袖の肩や袂に、やわらかい反射があるように思える。髪も光っているようだ。 茶室としてはむろん明る過ぎるのだが、それが令嬢の若さを輝かせた。娘らしい赤い袱紗も、甘い感じではなく、みずみずしい感じだった。令嬢の手が赤い花を咲かせているようだった。 令嬢のまわりに白く小さい千羽鶴が立ち舞っていそうに思えた。 -川端康成「千羽鶴」より |
これは情景描写であり、また人物の描写でもある文章ですが、
女性の「美しさ」「可憐さ」を表現した文章は数あれど、
この文章では、そのような直接的な表現を一切、使われていません。
まさに、その人物の「情景」を描写していくような形で、
その「美しさ」「可憐さ」を見事に描写している文章だと思います。
その「令嬢」の美しさ、可憐さを、
「やわらかい」(触覚)
「反射、光」(視覚)
「甘い」(嗅覚)
「みずみずしい」(味覚)
これら4つの感覚に訴える形で表現されているため、
まさに五感(聴覚は入ってませんが)で「美」を感じ取れるわけです。
ちなみにこの描写は、文中の「令嬢」が茶室でお茶をたてている所作で、
主人公の男性がそれを見て感じた事を文章にしている構図なのですが
「令嬢の手が赤い花を咲かせているようだった。」
という一文は、その令嬢がお茶を建てる「手先の所作」まで、
その「美」が浸透している要素を表現しているのだと思います。
そして、この小説の題名である「千羽鶴」が、この描写を締めくくります。
こんな文章を見せられると「〇〇のように美しい」といった、
ほぼ直接的な比喩表現などが、どこか安っぽい感じに思えてしまいますね。
このような「美」の表現も、川端康成は、やはり卓越していたわけです。
川端康成の「凄い」と思う情景描写③
|
山道に揺られながら娘は直ぐ前の運転手の正しい肩に目の光を折り取られている。黄色い服が目の中で世界のように拡がって行く。山々の姿がその肩の両方へ分かれて行く。 -川端康成「有難う」より |
山道を走る「馬車」の中で「娘」が先頭の運転手の背中を見つめている描写です。
本来は、そのような情景が先立つ形の上で読むべき文章ですから、
今一度、その情景を浮かべて読み返してみてください。
「山道に揺られながら娘は直ぐ前の運転手の正しい肩に目の光を折り取られている。」
この一文は娘が運転手の背中を見つめている客観視点の描写。
そして、次の一文からは、その「娘」からの視点に切り替わります。
「黄色い服が目の中で世界のように拡がって行く。」
黄色い服を着た運転手の背中をジッと見つめている娘の中で、
その情景、風景が娘にとっての「世界」となり、
その中で馬車が山道をどんどん進んでいく情景を
「山々の姿がその肩の両方へ分かれて行く。」
という文章で表現しています。
山道を進んでいく馬車の情景を「外側からの視点」ではなく、
その「内側からの視点(乗客である娘の視点)」に切り替えた上で、
そのイメージが鮮明に浮かぶような文章になっているわけです。
「山々が両肩に分かれて行く」
という表現で山道を進む馬車の情景を描写する、という視点、
そして、その感覚が、これもまた違い視点で「凄い」と思いました。
ちなみに、この「有難う」の娘は身内に「売り」に出されるところで、
その心情を交えて読むと、娘が運転手の背中を見つめている情景なども、
また、少し違った視点で見えてくるところがあると思います。
川端康成の文章に学ぶ、美しい情景描写。まとめ
以上、私が個人的に選んだ「川端康成の凄いと思う情景描写3選」でした。
川端康成の情景描写が卓越しているポイントは冒頭でもお伝えした。
・誰もが日常的に使っている言葉だけを使っている事
・日常的な言葉だけで全く新しい表現で文章を構成している事
・その表現が自然と頭の中に入ると共にイメージできる文章になっている事
この3点に集約されていると言っていいと思います。
文章には語藁力(たくさんの言葉を知っている)が必要と言う人もいますが、
コピーライティングにおいて言えば「多くの人が認知していない言葉」は、
単純に「反応の低下」を招きますので、あまり使うべきではありません。
そういった点で言えば、ここで挙げたような川端康成の情景描写は、
いずれも、誰もが日常的に使っている言葉だけで文章が作られているため、
コピーライティングの視点でもかなり勉強になる文章と言えるはずです。
川端康成の小説は、こんな卓越した描写のオンパレードですから、
もし、このような「卓越した表現力のある文章」に触れたい場合は、
そういう視点で、川端文学の世界に没頭してみるアリだと思います。
ちなみに私は師匠の薦めで「掌の小説」という短編集を読んでハマりました。
ここで挙げた「骨拾い」「有難う」も収録されていますので、
興味がありましたら、読んでみてください。
K.Uzaki
>コピーライティング至上主義者の会、コンテンツ一覧へ
タグ
2021年2月21日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:文学に学ぶコピーライティング
芥川龍之介「文章と言葉と」から読み解く「書く事」への拘り
芥川龍之介の短編?(散文?)に「文章と言葉と」という、
芥川龍之介が、題目の通り、文章や言葉について綴っている文章があります。
以下、その一部を引用します。
|
芥川龍之介「文章と言葉と」より 僕は別段必要以上に文章に凝ったた覚えはない。文章は何よりもはっきり書きたい。頭の中にあるものをはっきり文章に現したい。僕は只ただそれだけを心がけている。 (中略) 僕の文章上の苦心というのは(もし苦心といい得るとすれば)そこをはっきりさせるだけである。他人の文章に対する注文も僕自身に対するのと同じことである。はっきりしない文章にはどうしても感心することは出来ない。 |
芥川龍之介「文章と言葉と」から読み解く「書く事」への拘り。
芥川龍之介は言わずと知れた大作家ですから、
この「文章と言葉と」の中で芥川龍之介が言っている
「頭の中にあるものをはっきり文章に現したい」
というのは、おそらく「物語」や「小説」の事なのだと思います。
ですが、この「文章と言葉と」の中で芥川龍之介が主張している事は、
コピーライティングなどにも通じるものがあると思いました。
コピーライターが文章やコピーを書く際に「頭の中にあるもの」は、
他でもなく、そのコピーを介して「伝えたい事」「伝えるべき事」であり、
「はっきり書く」「はっきり文章に現す」
というのは「遠回りをしない文章を書く」と言い換える事が出来ると思います。
強いて伝える必要のない事をダラダラと伝えていくような、
無駄な文章は「書く行為」にも「読む方」にも何の得にもなりません。
文章そのものに凝るのではなく、また、その伝え方に苦心するのではなく、
「どうすれば伝えたい事をはっきりと文章にできるのか」
芥川龍之介が心がけていた事は「この一点」という事であり、
自分自身が「読む側」となった視点においても、それは同じと言っています。
要するに「伝えたい事をはっきりとした文章で伝えて欲しい」という事です。
そして「文章についての散文」は、このような一文で結んでいます。
| 僕は文章上のアポロ主義を奉ずるものである。僕は誰に何なんと言われても、方解石のようにはっきりした、曖昧を許さぬ文章を書きたい |
「方解石」のような文章を書く。
最後はいかにも時代の大作家らしいニーチェの「アポロ主義」と、
文章を石に例えた「方解石のように」という比喩。
アプロ主義は、芥川龍之介がどういう意味合いで用いたかはわかりませんが、
一般的な意味合いは「秩序や調和による統一を目ざす」という事らしいです。
平たく言えば、文章においては「合理主義」という事でしょうか。
方解石のように、は要するに「不純物の無い文章」という事だと思います。
とにかく「無駄な文章」「不要な文章」を取り除いた、
伝えるべき事だけをはっきりと伝えている文章を書く事。
これが芥川龍之介の「文章」に対して心がけている事であり、
また、文章を作っていく事への「苦心(こだわり)」だったようです。
そう考えると芥川龍之介は長編小説を書く事ができず、
実際、芥川龍之介の作品はいずれも短編小説ばかりです。
物語までも頭の中で簡潔にまとめてしまう思考だったのかもしれません。
それこそ、その物語で書きたい事、伝えたい事をはっきりと書いていくと、
おのずと、それは短編小説の範囲でまとまってしまったのではないかと。
アポロ主義者(合理主義者)が方解石のような文章を書いていれば、
物語や文章が簡潔なものになっていくのは当然かと思います。
大抵の有名な作家は何かしらの長編小説が出世作、代表作になっていますが、
その点、芥川龍之介は長編小説がなく(未完のものはいくつかあるそうですが)
全てが短編小説にも拘わらず、ここまで著名な作家になっているのは珍しいケースです。
まさに「無駄なのない文章によって作り出された簡潔な物語」が、
多くの人の支持を得ているからこそ、なのかもしれません。
コピーライターが「文章(コピー)」に心がけるべき事。
基本的に「コピー」も全く同じ事を伝えられているなら、
文字の数は1文字でも少なく、短い文章の方が反応も上がります。
まさに合理的に、方解石のような「無駄のない文章(コピー)を書く事が、
私達、コピーライターが心がけるべき重要なポイント課題でもあると思います。
もちろん「小説」と「コピー」は全く異なるものですが、
芥川龍之介の「文章と言葉と」に書かれている文章についての散文は、
・コピーライターが文章(コピー)に対して凝るべき事(こだわるべき事)
・コピーライターが文章(コピー)に対して心がけて苦心するべき事
これらそのまま書き表していると言ってもいいと思いました。
コピーライターこそ、アポロ的(合理的)な思考と文章で、
方解石のような無駄のない文章を書かなければならない、という事です。
もちろん、これは「当たり前」と言ってしまえばそれだけの話なのですが、
芥川龍之介のような著名な作家の「文章について」の文献を示せば、
その「説得力」が、何倍も増しますよね(笑)
これも文章で物事を伝える上でのテクニックの1つですから、
是非、参考にして頂ければと思います。
K.Uzaki
>コピーライティング至上主義者の会、コンテンツ一覧へ
タグ
2021年2月18日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:文学に学ぶコピーライティング
村上春樹の小説、文章に学ぶ比喩表現と隠喩表現の特徴と考察。
宇崎です。
今日は文章における「比喩」の講義をしたいと思いますが、
これは例文を挙げて進めていく方が分かり易いと思いました。
日本で「比喩が上手い」と言われている作家さんとしては、
やはり村上春樹さんがその筆頭に挙げられると思いますので、
今日はこんな題材で講義を進めてみたいと思います。
村上春樹の小説、文章に学ぶ比喩表現と隠喩表現の特徴と考察。
村上春樹さんの小説や文章はもともと好みが分かれると言われていて、
熱狂的なファンがいる反面、アンチと呼ばれる人も多いみたいです。
ただ、その要因の1つは村上春樹さんの小説(文章)が
他の作家の小説(文章)に比べて比喩、隠喩が非常に多い事と、
その内容の1つ1つがあまりにも「飛んでいる」ため、
そこを好きになれない人はどうしても受け入れられないのだと思います。
要するに、その比喩、隠喩を筆者と共有して楽しめるかどうかが、
村上春樹さんの小説を楽しめるかどうかの分岐点なんじゃないかと。
実際に、何かで読んだ事があるのですが「比喩表現の上手さ」を
「異なった二つのイメージ間のジャンプ力」
と考えた時に、その「ジャンプ力」を競い合えば、
村上春樹さんほど遠くに飛べる日本の作家はいないという事を
別の作家さんが村上春樹さんに向けて書いていました。
この評価が既に作家さんならではの比喩だな、と思いましたが
それくらい村上春樹さんの比喩は「飛んでいる」わけです。
そういうわけで、今日は実際に村上春樹さんの小説から、
幾つかの比喩表現を引用しながら「比喩」を
・コピーライティングに活用していく視点
・コピーライティングに活用していく方法
などを具体的に講義していきたいと思います。
尚、その上で実際に幾つか例文を引用していきますが、
ここでは「隠喩」も比喩の1つとして例に挙げていきます。
|
比喩:ある物事を、類似または関係する他の物事を借りて表現すること。 |
|
隠喩:比喩でありながら、比喩であることを明示する形式ではないもの。 |
比喩と隠喩(メタファーとも言います)の違いは上記の通りですが、
要するに「○○のように」「○○のような」というように、
それが「例え」である事が分かるように示されているものが比喩。
対して、その「のように」が示されていないものが隠喩であり、
どちらも分類としては比喩表現(たとえ)に変わりはありません。
ですので、この講義では、これに線引きをせずに例文を示していきます。
比喩を有効に活用する3つの視点。
まず、基本的な考え方として「比喩(たとえ)」を
文章上、有効に活用できるのは、どういう時かと言うと、
「読み手に鮮明なイメージを描いて欲しい時」
であり、特定の対象、物事、状況や心理、心情、感情など、
これらのイメージを読み手に伝えたい時に有効なものが比喩なんです。
「リンゴがあった」
「それは一瞬だった」
「彼女は笑った」
「私は悲しかった」
このように文章で物事、出来事、表情、心理を表現する時、
このままの表現では、その文章以上のイメージを与える事は出来ません。
その必要がないような場合は無理に比喩を使う必要もありませんが、
・それがどんなリンゴかを鮮明にイメージして欲しい
・それがどれくらい一瞬だったのかを伝えたい
・どんな表情で笑ったのかを頭の中に描いて欲しい
・どれくらい悲しかったのかを分かって欲しい
という場合、その対象の様子や度合いを比喩で例える事で、
その具体的なイメージを、より鮮明に読み手に伝えられるわけです。
そして、その具体的なイメージを頭の中に描かせていく事は、
それが小説であれば、物語に読者を引き込む上で重要になりますし
コピー(広告)においても、それは同じ事が言えます。
それを具体的に、鮮明にイメージさせる事が出来てこそ、
その物事に対する「共感」などを引き出し易くなるからです。
その上で、私が考える「比喩」の主な対象になるもの、
その対象にする事で有効な効果を生み出すものは、
・目に見えるものを対象とする比喩
・目に見えないものを対象とする比喩
大きく分けて、この2つに分類され、
これらは更に以下のように分類する事が出来ます。
|
(目に見えるものを対象とする比喩) ・特定の対象(モノ)を具体的にイメージさせるための比喩 ・表情から見える心理を具体的にイメージさせるための比喩 |
|
(目に見えないものを対象とする比喩) ・目に見えない対象をイメージさせるための比喩 ・心理、心情をイメージさせるための比喩 |
では、この分類を前提に実際に村上春樹さんの小説から、
幾つか、例文を挙げていきたいと思います。
特定の対象(モノ)を具体的にイメージさせるための比喩。
|
白いたつまきが空に向かってまるで太いロープのようにまっすぐたちのぼっている。 引用:海辺のカフカ |
|
陰毛は行進する歩兵部隊に踏みつけられた草むらみたいな生え方をしている。 引用:1Q84 |
|
スカートはぐっしょりと濡れて彼女の太腿に身寄りのない子供たちのようにぴったりとまつわりついていた。 引用:世界の終りとハードボイルドワンダーランド |
上記は「たつまき(の様子)」「陰毛(の生え方)」といった
特定の対象(モノ)とその様子を比喩で表現しています。
・まるで太いロープのように
・行進する歩兵部隊に踏みつけられた草むらみたいな
・身寄りのない子供たちのように
このような「視覚的な描写」を用いて、その対象の様子を、
より視覚的にイメージできるようにしているわけです。
ただ、ここで挙げた例は視覚的なイメージのみを広げるもので、
この「特定の対象(モノ)」に対して用いる比喩は、
その対象を目にしている人物の心理や心情を表す事も出来ます。
|
ビニール・ラップを何重にもかぶせたようなぼんやりとした色の雲が一分の隙もなく空を覆っていて、そこから間断なく細かい雨が降りつづいていた。 引用:世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド |
これも「雲(の様子)」に対しての視覚的な比喩ですが、
「ビニール・ラップを何重にもかぶせたような」
という雲の表現は、その雲を目にしている人物側の心理も、
同様の心理である事を表現できる効果を生んでいると思います。
つまり、この「特定の対象(モノ)」に対して用いる比喩は、
・その対象のイメージをより鮮明にできる
・その対象を目にする人の心理を表現する
このような2つの効果を有効に担う事が出来るということです。
表情から見える心理を具体的にイメージさせるための比喩。
|
彼は一人息子の写真でも見せるようににっこりと微笑みながら 引用:羊をめぐる冒険 |
|
彼女は気取ったフランス料理店の支配人がアメリカン・エクスプレスのカードを受け取るときのような顔つきで僕のキスを受け入れた 引用:国境の南、太陽の西 |
|
木の葉の間からこぼれる夏の夕暮れの最後の光のような微笑みだった 引用:ダンス・ダンス・ダンス |
上記はいずれも「表情」をイメージさせるための比喩で、
その比喩によって、表情の裏にある心理を描写しています。
嬉しそう、哀しそう、笑っている、泣いている、といったように、
人の表情を率直に表現できる言葉は幾つかあると思いますが、
これだけではその鮮明なイメージや心理を描写する事が出来ません。
とくに小説などは、その心理描写などが重要になるため、
表情にはこのような比喩表現が多く用いられる傾向にあります。
逆にコピー(広告)の文章においては、
あまり活用する事はない比喩表現かもしれませんが、
小説を書くのであれば、避けられないものだと思います。
目に見えない対象をイメージさせるための比喩。
|
予言は暗い水みたいにそこにあった。 引用:海辺のカフカ |
|
「もしもし、」と女が言った。それはまるで安定の悪いテーブルに薄いグラスをそっと載せるようなしゃべり方だった 引用:風の歌を聴け |
これは「目に見えない対象をイメージさせるための比喩」であり、
上記は「予言」や「しゃべり方(声色)」が比喩の対象になっています。
「予言」も「しゃべり方(声色)」も、目に見えるものではありません。
故に、それがどういうものかをイメージさせたい場合は、
やはり、そこに比喩を用いていく必要があるんです。
それが目に見えないものであるからこそ、
文章でそれをたとえて描写する必要があるという事です。
心理、心情をイメージさせるための比喩。
|
時間のことを考えると私の頭は夜明けの鶏小屋のように混乱した。 引用:世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド |
|
いろんな出来事が回転木馬のように接近したり離れたりしていた。 引用:世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド |
これも同様に目には見えない心理や心情、
その人物の「頭の中」を表現している比喩であり、
やはり「心理」や「感情」のようなものは目には見えないため、
それを鮮明に伝えるには比喩を用いていく必要があります。
喜怒哀楽はもとより、上記のような「混乱」や「迷い」など、
その心理を鮮明に描写するには比喩が不可欠なわけです。
有効な比喩の作り方。
ここまでで例に挙げた比喩表現は全てそうなのですが、
比喩はやはり「視覚的なイメージ」を引き出す事が有効であり、
「その対象を視覚的なイメージ(目で見える何か)に例える」
という手法が最もオーソドックスです。
ただ、これは絶対にそうでなければならないという事ではなく、
嗅覚、感覚、味覚、聴覚を対象とする表現でも問題ありません。
|
プレイヤーの針をターンテーブルのかどにぶっけたときのような不自然に誇張された音が耳の中に響きわたった 引用:世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド |
これは「聴覚」を対象とする比喩になっている事が分かると思います。
つまり比喩は五感のいずれかに訴えかける表現が有効であるという事です。
ただ、その中でも、最もイメージを広げやすく、たとえ易いものが
視覚を対象とする表現であるため、比喩表現は全体的に、
視覚的な表現を用いたものが多い傾向にあります。
その上で、コピー(広告)の文章やメルマガの文章などにおいても、
・目に見えない対象をイメージさせるための比喩
・心理、心情をイメージさせるための比喩
この2つの比喩を有効に活用できる余地は大いにあるはずです。
ただ、ここで例に挙げていったような村上春樹さんレベルの比喩は、
正直、センス・・・としか言いようがないもののような気がします。
何せ、アジア圏で初の「フランツカフカ賞」を受賞し、
ノーベル賞候補にも挙がっている世界的な作家さんですからね。
正直、ここまで「飛距離のある比喩」はコピー(広告)には、
必要ないと思いますので、世界的な作家を目指すような人以外は、
無難な比喩(たとえ)を用いていく範囲で十分だと思います。
少なくとも、コピー(広告)を担う文章において、
比喩は、上手く使えると有効なものではありますが、
強いて必要不可欠というほどのものではありませんので。
ですが、小説などを読んでいくと、
心に残る比喩が出て来る事もあると思いますので
そういうものは頭に留めていくのも1つの手かもしれません。
そういう意味では村上春樹さんの小説は「比喩の宝庫」だと思います。
どの小説のどのページに目を落としても比喩が出てきますからね。
村上文学が苦手という人も、そういう見方をすると面白いかもしれません。
その比喩の1つ1つを今回の講義内容と照らし合わせてみてはどうでしょうか。
是非、参考にしてみてください。
K.Uzaki
>コンテンツ一覧へ
タグ
2017年9月8日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:文学に学ぶコピーライティング
小説の出だし、冒頭文の書き方に学ぶ文章を読ませるテクニック。
宇崎です。
今回は小説や文学作品の「出だし(冒頭文)」から、
「文章を読ませるテクニック」
にあたるものを言及してみたいと思います。
有名な小説や「名作」と言われる文学作品は、
やはりその出だしとなる冒頭文から光るものがあり、
「読者を即座に引き込むテクニック」
がさりげなく用いられている傾向にあるんです。
ただ、それは作者が「意図的」にそうしたのか、
意図しない文章が結果的にそういう文章になったのか、
それは作者以外、知る由もないところかと思います。
何せ、そういう小説や文学作品を世に残した人は、
いわゆる「天才」と言われる文豪達がほとんどですからね。
ですが、これから挙げていく有名な小説や文学作品などには、
その出だし(冒頭文)に共通するものがありますので、
今回の講義では、そのような天才達が手掛けた文章から、
「読者を引き込む文章のテクニック」
にあたるものを紐解いてみようと思います。
|
このブログで扱っているテーマはあくまでも、 「コピーライティング」 であり、文章によって読み手を反応させるスキルや、 それに準じたテクニックにあたるものです。 ただ、そのコピー(文章)で実際に反応を得るには、 大前提として、それをまず読んでもらう必要があります。 商品の広告(販売)などを担うコピー(文章)は、 読んでもらえる事が前提になるわけではないからです。 故にコピー(文章)は「読まれない事」を前提とした上で、 「読ませる事(興味を引く事)」 を意識して見出しや冒頭文を構成する必要があり、 これが最初に超えるべき「消費者心理の壁」にあたります。 コピーライティング界隈では、 ・興味の壁(Not Read):読まない ・信用の壁(Not Believe):信じない ・行動の壁(Not Act)・行動しない これが消費者心理における3つの壁と言われていますが、 今回の講義はこの3つの壁の中の「最初の壁」である、 興味の壁を超えるテクニックを言及するものだという事です。 |
それでは、早速、いってみましょう。
小説の出だし、冒頭文の書き方に学ぶ文章を読ませるテクニック
まず、結論的なところから言ってしまうと、
多くの有名な小説や名作と言われる文学作品の多くには、
その出だしの冒頭文に以下のような共通点があります。
・感覚(五感)に訴えている
・普遍的なテーマを意識させている
基本的には、この「どちらか」に当てはまる出だしから始まり、
読者を物語へと一気に引き込むような構成になっているわけです。
もちろん、全てがこのどちらに当てはまるわけではありませんが、
わりと、このどちらかのテクニックを使っているものが多く、
前者の「感覚(五感)に訴える構成」は以下のようなものです。
|
道がつづら折りになって、いよいよ天城峠に近づいたと思う頃、雨足が杉の密林を白く染めながら、すさまじい早さで麓から私を追ってきた。 ―『伊豆の踊子』川端康成 |
|
国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。 夜の底が白くなった。信号所に汽車が止まった。 ―『雪国』川端康成 |
|
「おい地獄さ行ぐんだで!」 二人はデッキの手すりに寄りかかって、蝸牛が背のびをしたように延びて、海を抱え込んでいる函館の街を見ていた。 ―『蟹工船』小林多喜二 |
|
朝、食堂でスウプを一さじ、すっと吸ってお母さまが、 「あ」 と幽かな叫び声をおあげになった。 ―『斜陽』太宰治 |
|
飛行機の音ではなかった。耳の後ろ側を飛んでいた虫の羽音だった。 ―『限りなく透明に近いブルー』村上龍 |
いずれも有名小説や名作と呼ばれる文学作品の出だしの一文ですが、
これらは主に「視覚」か「聴覚」または、その「両方」の感覚に訴え、
そのイメージを頭の中で描けるような冒頭文になっている事が分かります。
川端康成などは、上記以外も「描写形」の冒頭文が多い作家なので、
もしかすると、意図的にこの手法を使っていたのかもしれません。
また、上記で挙げた『蟹工船』などに見られる、
「台詞」
から始まる冒頭文もわりと王道的なもので、
それ自体が、その台詞が耳に入るような感覚や、
その「会話」のイメージを広げ易い傾向にあるため、
台詞が出だしとなっている小説はわりと多い傾向にあります。
このような視覚、聴覚など感覚に繋がる文章は、
それらによって頭の中に「イメージ」が広がる事となり、
そのイメージによって読者は物語に引き込まれる事になるのです。
感覚(五感)に繋がる文章で読み手を引き込む。
対して、出だしの冒頭文で
「普遍的なテーマを意識させているもの」
としては、以下が該当すると思います。
|
永いあいだ、私は自分が生まれたときの光景を見たことがあると言い張っていた。 ―『仮面の告白』三島由紀夫 |
|
死のうと思っていた。 ―『葉』太宰治 |
|
山椒魚は悲しんだ。 ―『山椒魚』井伏鱒二 |
三島由紀夫の『仮面の告白』は「生(誕生)」というテーマ、
太宰治の『葉』は「死」という普遍的なテーマを意識させています。
井伏鱒二の『山椒魚』は「悲しみ」という普遍的なテーマに、
山椒魚という本来は感情を持たない生き物を絡ませて、
ある種の「意外性」を持たせていますね。
ただ、いずれも「続き」が気になってしまう冒頭文ではないでしょうか。
やはり、このような普遍的なテーマにあたるものには、
誰もが少なからず「興味」や「関心」があるため、
それを意識させる冒頭文には引き込まれてしまうのだと思います。
ちなみに私は最初に例を示した感覚(イメージ)に繋がるものよりも、
後者の「普遍的テーマ」に繋がるものの方が引き込まれるのですが、
この「両方」を押さえている冒頭文が以下などです。
|
死者たちは、濃褐色の液に浸って、腕を絡みあい、頭を押しつけあって、ぎっしり浮かび、また半ば沈みかかっている。 ―『死者の奢り』大江健三郎 |
|
「完璧な文章などといったものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね。」 ―『風の歌を聴け』村上春樹 |
|
さびしさは鳴る。耳が痛くなるほど高く澄んだ鈴の音で鳴り響いて、胸を締めつけるから、せめて周りには聞こえないように、私はプリントを指で千切る。 ―『蹴りたい背中』綿矢りさ |
大江健三郎の『死者の奢り』は「死後の世界」というテーマに、
視覚的なイメージが広がる描写を文章にしたもの。
村上春樹の『風の歌を聴け』は「絶望」というテーマに、
台詞を出だしの冒頭文に使うテクニックを重ねているもので、
綿矢りさの『蹴りたい背中』は「さびしさ」をテーマに、
聴覚と視覚のイメージに繋がる文章が構成されていると思います。
もちろん、ここで挙げたものは、ごく一部でしかありませんので、
・感覚(五感)に訴えてイメージを引き出す
・普遍的なテーマを意識させる
このいずれか、もしくは両方を押さえて、
その出だしの冒頭文を構成している小説や文学作品は、
本当に数えきれないほど、多くあるわけです。
そして、これらの要素を押さえた文章の有効性は、
コピーライティングの観点でも全く同じ事が言えます。
・鮮明なイメージが膨らむ文章
・普遍的なテーマを意識させる文章
これらに相当するコピーは読み手を一気に引き込み、
その続きを読ませる上でも極めて有効であるという事です。
少なくとも、これらのテクニックを用いた「事例」にあたるものは、
多くの有名な小説や名作と呼ばれる文学作品で確認できるはずですので、
今後は、そのような視点でそれらに目を通してみてください。
また、違った気付き、学びを得られるはずです。
K.Uzaki
>コンテンツ一覧へ
タグ
2017年8月8日 | コメントは受け付けていません。 |
カテゴリー:文学に学ぶコピーライティング